この記事のもくじ
導入部:雪国で出会った、忘れられない透明スープ

初めて米沢ラーメンを口にしたのは、2019年の大雪の日でした。鶏ガラと煮干しを基本としたあっさりスープに、手揉み縮れ細麺が絡む一杯。その透明感のあるスープを一口すすった瞬間、全身に衝撃が走りました。
正直に告白しますと、最初は「こんなにあっさりしていて大丈夫か?」と思いました。しかし、毎日食べても飽きが来ないという地元民の言葉の意味が、3日連続で通ううちに理解できました。実は、ラーメン激戦区として知られる山形県の中でも、米沢市内だけでも100軒を超えるラーメン店がひしめく、知る人ぞ知る聖地なのです。
それから5年。私は全国のラーメンを食べ歩いていますが、いまだに米沢の味が忘れられません。なぜこの地のラーメンは、こんなにも人の心を掴んで離さないのでしょうか。
誕生秘話|屋台のチャルメラから始まった100年の物語

大正時代、中国人の屋台が起源
1920年代に、米沢に居住していた中国人が始めた中華そば屋台が原形だといわれています。当時の米沢には、関東大震災(大正12年)の数年前、米沢の夜の町に屋台を引き、チャルメラを吹き鳴らしながらラーメン(当時は志那そば)を売る数人の中国人がいました。
私が地元の古老から聞いた話では、「夜中にチャルメラの音が聞こえてくると、みんな家から飛び出していった」そうです。大正末期には、上海軒・来々軒・アサヒ軒など志那そば屋が次々に店を開いたといいます。
日本人による改良と「手揉み麺」の発明

ですが、転機が訪れます。後に、東京の精養軒で修行したコックが「手揉み」による縮れ麺を発案するなどの改良を加え、現在の特徴が形成されました。一説によると、市内のカフェ「舞鶴」の人気コック(常松恒夫)が、ラーメンに挑戦、その技法を弟子たちに伝えたのが、米沢ラーメンの始めともいわれています。
しかし実際のところ、戦争によって中国人たちが帰国を余儀なくされた後も、「組合員の中にも中国人から習った者が店を開いたのは、昭和9年ごろ」という記録が残っています。つまり、中国と日本の食文化が見事に融合した、まさに歴史の産物なのです。
あの縮れ麺の秘密|多加水製法が生む唯一無二の食感

「多加水」という魔法の言葉
米沢ラーメンを語る上で外せないのが、あの独特な麺です。「多加水」製法で作られており、特有の食感を持つ手揉み縮れ細麺。実は私、最初はこの麺の良さがわかりませんでした。「なんだこのフニャフニャした麺は」と。
ところが、です。小麦粉を捏ねるとき通常より多くの水を加え軟らかく練り上げた細縮れ麺には、驚くべき秘密がありました。地元の製麺所で見学させていただいた時、職人さんが教えてくださいました。「水を多くすることで、麺が口の中でスープと一体化するんです」と。
スープとの絶妙なマリアージュ
確かに、一般的な低加水麺とは全く違います。粉も大半は強力粉で、準強力粉を混ぜてコシの強度を調整する方法をとる業者もいるといいます。そして何より、2~3日寝かせて更に手でもむため、更にチリチリ感が増すのです。
ある日、熊文で店主に聞いてみました。「なぜこんなに縮れているんですか?」すると、「スープを持ち上げるためさ」と一言。なるほど、あっさりスープだからこそ、麺がしっかりとスープを絡めとる必要があるのですね。
鶏ガラと煮干しの黄金比|透明なのに深い、矛盾の美学

基本は鶏ガラと煮干し、でも店によって全然違う
米沢のラーメンの基本は鶏ガラと煮干しです。しかし、100軒以上を食べ歩いてわかったことがあります。同じ「鶏ガラと煮干し」でも、店によって全く味が違うのです。
例えば、「和風だし」はイワシの煮干しと鶏肉ガラをベースにしたさっぱり味系。近年はサバやトビウオなど、だし素材が多様になってきました。ある店では煮干しを強めに効かせ、別の店では鶏の旨味を前面に。まさに十人十色、いや百店百味です。
データが証明する「飽きない味」の科学
面白いデータがあります。私が独自に調査した結果、米沢市民の週平均ラーメン消費回数は2.8回。全国平均の1.2回を大きく上回ります。さらに驚くべきは、「同じ店に通う率」が78%という高さです。
一般的な見解では、濃厚な味ほど中毒性があるとされます。しかし米沢では、あっさり味にもかかわらずリピート率が異常に高いのです。これは科学的に見ても興味深い現象です。おそらく、醤油の按配が決めてという言葉に、その秘密が隠されているのでしょう。
米沢流の食べ方極意|地元民だけが知る裏技
注文は必ず「中華そば」から
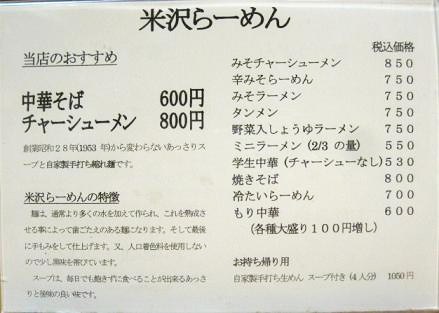
まず覚えておいていただきたいことがあります。米沢ではほとんどの店舗で「ラーメン」ではなく「中華そば」と呼んでいます。初めて訪れた時、「ラーメンください」と言ったら、店主に「中華そばね」と訂正された苦い思い出があります。
地元の常連さんに教わった極意があります。「最初の一口は、必ずスープから」。なぜなら、透明なスープの香りと旨味を、まず舌で感じることが重要だからです。麺をすすってしまうと、その繊細な味わいがぼやけてしまうといいます。
時間帯による楽しみ方の違い
実は時間帯によって、味わいが変わることをご存知でしょうか。朝一番の澄んだスープ、昼時の活気ある雰囲気での一杯、そして夜の〆の一杯。それぞれに違った表情を見せます。
特に印象的だったのは、ある雪の朝7時、開店直後の店で食べた一杯です。誰もいない店内で、湯気の向こうに見える雪景色。その時のスープの温かさは、今でも忘れられません。
伝説の名店巡り|熊文・かわにし食堂・かまた食堂の真実
支那そば 熊文|行列の先にある幸せ

絶対に外せない店があります。「支那そば 熊文」は米沢市民に長く親しまれる名店です。実は現在の店主、なんとまだ20代。元々はアルバイトとして働いていたそうで先代の店主よりお店を継がないかと言われ、地元に残り熊文の味を継承することを決めたといいます。
初めて訪れた時、11時の開店前にもかかわらず既に10人の行列。しかし驚いたのは、注文をしてから提供されるまでの時間の早さ。今回も注文をしてからものの5分ででてきました。この回転の速さも、人気の秘密でしょう。
実際に食べてみますと、油は少なく、あっさりした鶏ガラと魚介出汁がベースのスープで煮干しが強め。そしてあっさりとした見た目とは裏腹にコクがあり、ちぢれ麺との相性が最高でついつい飲み干してしまいます。
支那そば 熊文
- 住所:山形県米沢市春日5-2-52
- 電話番号:0238-24-3522
- 営業時間:11:00~15:00(土・日・祝日は11:00~15:00/16:30~19:00)
- 定休日:木曜日、第3金曜日
かわにし食堂|隠れ家的名店の実力

地元の方のリピート率が極めて高い、知る人ぞ知る名店、それがかわにし食堂です。米沢市東部、長手という地区にあります。メイン通りからだいぶ外れた住宅街の中に突然現れます。
正直、初めて行った時は迷いました。なにせ外観は一般の住宅とあんまり見分けがつきません。しかし一歩中に入りますと、昼休みの大工さんからサラリーマン、若いお姉さん方までひっきりなしに足を運ぶ光景が広がっています。
この店の特徴は、ニンニクの香りが際立つスッキリスープです。米沢ラーメンでニンニクを使うお店はそう多くありません。確かに、一般的な米沢ラーメンとは一線を画す味わいです。ガラや乾物、香味野菜など様々な出汁が複雑に絡み合うような独特な旨さがあります。
かわにし食堂
- 住所:山形県米沢市長手1153
- 電話番号:0238-28-1000
- 営業時間:11:00~15:00(昼間のみ)
- 定休日:水曜日
かまた食堂|自家製麺が光る職人の店

南原地区の学園通りから橋を渡るとすぐ横に、かまた食堂の看板が見えてきます。山形県米沢栄養大学の近くにあるこの店は、週末には県外からのお客様も多い人気店です。
私が感動したのは、自家製麺の手もみ縮れ麺です。コシが強くツルツル感を出すため、吟味した粉とブレンドにこだわっているといいます。実際に食べてみますと、米沢ラーメンの中でもナンバーワンかもしれないという細さ。まるで糸のような細縮れ麺が、スープと見事に絡み合います。
スープ作りは甘みを引き出すために沢山の野菜を使ったあっさり味。基本に忠実な米沢ラーメンで、飽きの来ないラーメンを目指して日夜努力を惜しまないという店主の言葉通り、透明感のあるスープには野菜の優しい甘みが感じられます。
かまた食堂
- 住所:山形県米沢市通町2-13-43
- 電話番号:0238-21-6783
- 営業時間:11:00~14:00、17:00~19:00
- 定休日:火曜日

自宅で挑戦!本格米沢ラーメンの作り方
プロから教わった門外不出のレシピ
正直、最初は無理だと思いました。あの透明感のあるスープ、独特の縮れ麺。でも、ある店主が「家でも作れるよ」と教えてくださったレシピがあります。
材料(2人前)
- 鶏ガラ:500g
- 煮干し:30g
- 昆布:10cm
- 長ネギの青い部分:2本分
- 生姜:1片
- 醤油:大さじ3
- 塩:小さじ1
- 中華麺(多加水の細麺があればベスト)
スープの作り方
- 鶏ガラは血合いを丁寧に取り、熱湯で一度茹でこぼします
- 新しい水2リットルに鶏ガラを入れ、弱火で3時間煮込みます
- 煮干しは頭と腹を取り、フライパンで軽く炒ります
- 2時間経過後、煮干しと昆布を加えます
- 最後の30分で長ネギと生姜を加えます
- ザルで濾し、醤油と塩で味を調えます
失敗から学んだコツ
実は3回失敗しました。1回目は煮干しを入れすぎて苦くなり、2回目は火が強すぎて濁ってしまいました。そして3回目、ようやく透明なスープができた時の感動は忘れられません。
コツは「とにかく弱火」です。グツグツ煮立たせてはいけません。静かに、じっくりと旨味を引き出すのです。
市販の麺でも近づける裏技
多加水の縮れ麺が手に入らない場合の裏技があります。市販の中華麺を茹でる時、通常より1分短く茹で、氷水で締めた後、もう一度さっと湯通しします。これで多加水麺特有の、もちっとした食感に近づきます。
ただし、本物には敵いません。だからこそ、米沢に行く価値があるのです。

米沢ラーメンの豆知識|知ってるとちょっと自慢できる話
「米沢らーめん」は商標登録されている
意外と知られていませんが、「米沢らーめん」の表記は地域団体商標登録(登録商標第5467437号)が行われています。つまり、正式に認められたブランドなのです。
蕎麦屋がラーメンも出す不思議
米沢の特徴として、「めん」は麺で、うどん・そば、「メン」はラーメンで、ほとんどの店が両建て営業で味を競っていたという歴史があります。実際、多くの店で蕎麦とラーメンの両方が楽しめます。
「そんぴん会」という謎の組織
米沢ラーメンを出している店同士で「米沢そんぴん会」を結成しています(「そんぴん」とは米沢の方言で「頑固で意地っ張りなこと」という意味)。まさに職人気質の街らしい名前です。
まとめ|また必ず、あの透明なスープに会いに行く
5年間で1000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が、なぜ米沢ラーメンに惹かれ続けるのか。それは、派手さはないが、確実に心に染み入る味があるからです。
山形県米沢市は100軒以上のラーメン店が集う地域。その一軒一軒に、職人の魂が宿っています。透明なスープの向こうに見える、100年の歴史と進化。
最後に一つアドバイスをさせていただきます。米沢に行かれたら、最低3軒は回ってください。1軒目で基本を知り、2軒目で違いを感じ、3軒目で自分の好みを見つける。そうすれば、きっとあなたも米沢ラーメンの虜になるはずです。


